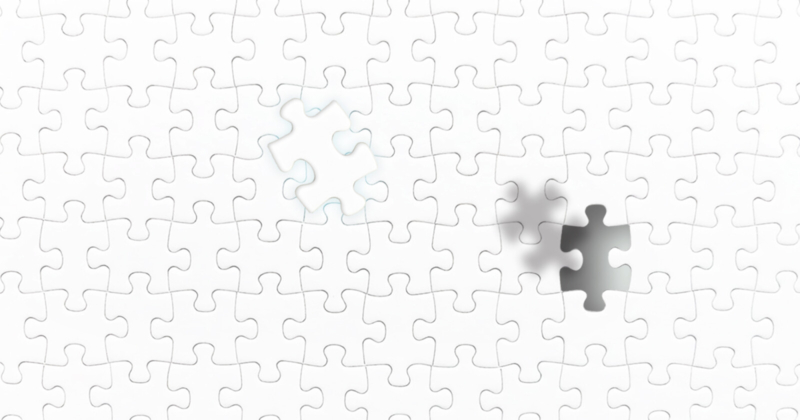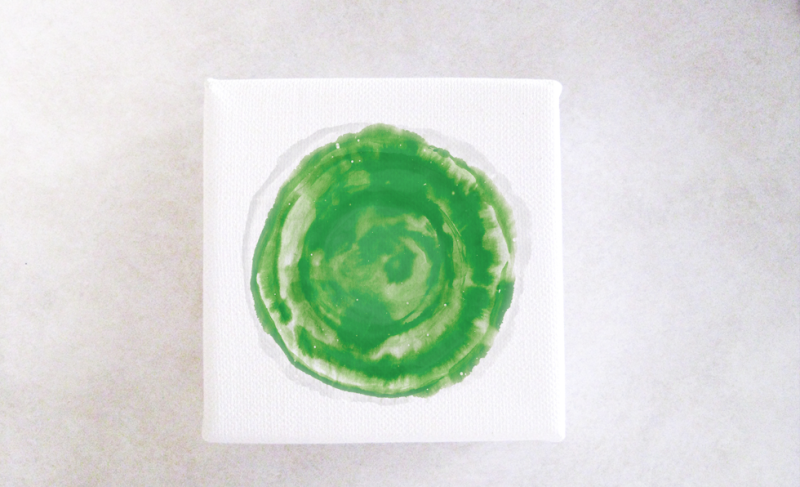——— 大人になるたびに夏が好きになる自分がいる。
私はまだ現在よりも若い年齢の頃、夏よりも断然、冬が好きだった。いまでももちろん冬は好きだ。きりっとした空気が頭をひきしめてくれる。そして冬の方があたたかさをより感じるからだと思っている。そんな私がいつからか夏が好きになっていった。
夏が好きになった理由は特にはなくて、年齢を増すごとに単純に寒さに耐えられなくなった自分もいるのかもしれないが、いつからか、なぜか夏は懐かしくなったんだ。夏休みやいまにして思えば久遠のように長い時間のあった子供の頃の感覚からの影響で、きっと思い出という夏があるからなのだと思う。
そんな思い出という記憶が脳にあるのか、心や意識の中にあるのか、または全く別の場所にあるのかは定かではないが、まるで夏自体が記憶を持っているかのように感じるくらいに、夏には幻想に似た淡い水色の景色を映す時空間がこの世界と交差してしまっているのではないかと錯覚するような感覚。あの青い空や白い雲を見るだけで蘇る景色や感覚が、もはや夏自体に記憶されているようにも思えてくる。
冬産まれの私が夏を好きになってきたのは、いつ頃からだろう。たぶん20代後半から徐々に徐々に、理由も無く夏が好きになってきた。たぶん理解されない表現かもしれないが、思い出が一周したのだと思う。いま現在に体感して自分が存在している夏の季節や時間、夏の一日のそれ自体がまるで思い出のように感じ始めて、透き通る透明な思い出がぼんやりと現実と重なり、蜃気楼のように混ざっているかのような夏の大気の感覚がいつからか芽生え始め、歳をとればとるほど夏が好きになってきたのだ。
人の記憶の箱の大きさが皆同じだとすれば、その記憶の箱は、つまりは人生の記憶ということになる。そして誰ものその箱の容積が同じならば、長生きしても短命だったとしても箱の重量や容量は同じ。つまり、人生の時間の重さや容量は誰もが同じということだ。付け加えるなら人間だけでなく、アリでもネズミでもゾウでもクジラでも、1000年以上生きる森の木々や、例えるなら何万年や何億年もかけて形を成している鉱物や惑星などでも、それは同じと言えることだろう。
産まれて一年の子供も100歳の老人も、記憶の箱の大きさは皆同じなのだ。同じ10立方cmの器なら、その器は産まれた瞬間からもう既にいっぱいで、100歳なら100年分で満たし、1歳であれば一年分の大切な大切な人生の時間が、溢れんばかりにその箱を満たしている。人の一生とは、そういうものだと思う。
今の私の人生の箱には、40回以上の夏が入っている。夏至を境に、冬至の頃などを軸にして、フクロウの飛び立ったあとの長い夜の訪れる冬の期間に比べ、青い空と白い雲を仰ぎながら、鳴き蝉の雨音を子守唄に昼寝をしても尚、夕暮れ時までいつまでも時間のあった、陽の長い夏の記憶はそれだけ多く含まれているのだろう。
思えば大人になればなるほど、夜の生活が長くなるものだ。たぶん昼間は、仕事などの義務を果たす時間に奪われ、やっと自分に戻れるのは夜になり、夜は体よりも思考の中での思案の時間が多く、もっとも夜中とは一般的に人は、ほぼ睡眠しているのだから、そんな夜の記憶は実像としての記憶ではない未記録のようなものとして、箱に残らないものも多いのかも知れない。
この箱もまだ余裕のある器なのかもしれないが、20個の夏で収まっていた頃よりも現在のほうが、さすがに記憶も少し圧迫され圧縮もされるらしく、20代なんてついこの間のことに感じる。それよりももっと幼い記憶も、だいぶ近くなってきたみたいで、最近ではよく思い出される。そんな圧縮された記憶の箱のせいなのか、どうりで、一日が早く感じるわけだ。
思い出が一周したというのは、なんとも説明がつけられないのだが。私の中では、一周したという表現が一番しっくりくるのだ。毎年の同じ時期になると「また夏が来た」という言葉が脳裏にリアルに浮かんでは、箱をひっくり返して思い出がとっちらかって混ざってしまったかのような、また夏が来る。同じ瞬間などは一切ないはずなのに、なぜか夏はいつでも夏で、いまになっても子供の頃に居た、あの夏が毎年訪れているかのような感覚なのだ。
記憶の箱の中に、ある意味で夏というジャンルが圧縮して纏められ、ちょうどそのころから人は、本来は遠いはずの思い出話を、昨日のことのように喋りだす。そして今、また今年も私は、記憶の箱の中から『夏』というタグの付いた思いを出そうとしているのだろう。
青い空や眩しさに目を細めながら、遠くに目を送ったまま見ていた白い大きく連なる入道雲や、遠くに見えた逃げ水の蜃気楼のような、あの頃の僕。きっとあの頃はいつもずっとずっと未来を見ていた。今年の私はなにを遠くに眺めているのだろう。まるでなにかをいつも待ち望んでいたかのように、ずっと遠くを見ていた眼差しの向こうに、いまではそんな少年の僕が見えている。追いかけられなかったいくつもの記憶に再会できるように、会ってちゃんとこんどは手を振れるように、今年は長い夏を過ごそう。
大きな瞳に流れる雲や青く映り込んだ未来の空を、夢にしないで一所懸命に描きながら仰向けになって、あの少年の横で大の字で同じ夏を精一杯生きてみたいと思っている。いつかこの記憶の箱の蓋を閉じて、私も私ではなくなることは知っている。けれどそんな頃にでも、きっと別の記憶の箱に私が少しでも残ってしまうことだろう。私の箱の中にも親兄弟や子供の頃の家族や友達やたくさんの人との景色が入っている。
思えば子供の頃、母はきっと愛の女神で、父はいつの時も僕の正義の味方だった。そんなふうにいつか誰もが大人になって、いつか季節が何周も巡ってきっと誰にでも夏がまた来て、きっと誰かの夏の一日がまたいっぱいに箱を満たす。あっという間に過ぎて行く押しつぶされた記憶のいまになって、まだまだ幼かった頃の満たされた夏の質量が、いまでも全体の半分以上を占めている気がする。
そんなふうにきっと、まだはじまったばかりの頃は、なにもかも新鮮ですべてが発見の連続で、大きな空を泳ぐ雲や大きな海を渡る風のように命が眩しいほどに生きて、草木や花や鳥や蛙や蝶蝶とも話すことが出来たような長い長い一日であふれんばかりに満たしている夏。そんな誰かの記憶の中の私もひとりになるのだろう。その記憶の箱を、まるで魔法のようにまっすぐに大切に見守ることが、いまでは私の、大人の僕の夏なのだ。
20070920(20180502 3:35編集)